必至問題とは?
皆様は「必至問題」というものをご存じでしょうか?
「詰め将棋」や「次の一手」はほとんどの方が体験していると思います。
ですが必至問題は意外とマイナーで、知らない方も多いようです。
必至問題とは
設定局面から王手か詰めろの連続で迫り、最後に必至をかける
という問題です。
なお「詰めろと必至」の詳細に関してはこちらをご覧下さい。
ここまで簡単に必至問題について紹介しましたが、実はかなり難しく、敬遠されるかたもいらっしゃいます。
1番やさしい「1手必至」でも、です。
僕も苦手分野の1つとなっており、結構苦労した経験も。
ではどうして難しいのか?
それをこれから紹介します。
意外に難しい必至問題
まずはこちらをご覧下さい。

図は▲2三銀と必至をかけた局面です。
この図になったら、後手はどう受けても詰みを免れることはできません。
ですがそれはあくまでも
先手が正しく攻めてきたら
の場合で、当然ながら後手も最善策を尽くしてきます。
先手がそれらをすべて読み切り、後手玉の詰みを読み切るまでが「必至問題」であり、本当に難しい。
今回も後手がこう粘ってきたら、どうでしょうか(粘る図)。

後手は△2二飛と粘ってきました。
それでも先手が最善策を尽くすと、
▲3三桂 △1一玉 ▲2一金 △同飛
▲同桂成 △同玉 ▲2二飛 △3一玉
▲3二と(読み切った図)

までの詰みです。
ですが▲3三桂と詰ましに行ってから、9手かかっています。
詰め将棋だと9手詰め。
初心者や初級者の方では、完璧に詰ますのは厳しいと思います。
こういった現実があるため、必至問題は敬遠されているイメージがあります。
必至問題は相手の応手などもすべて読み切る必要があるため、これを克服すると確かに読みの力がつき、実力もアップします。
ですが現実は、本当に難しい。
なので初心者や初級者の方は
盤に並べて解説を読みながら解く
方法をおすすめします。
最初はわからなくても構いません。
並べていて
相手のこういった粘り方もあるんだな
くらいの気持ちで挑んでOKです。
それを繰り返していくうちに、少しずつ上達していくと思います。
応手が読み切れなかった必至問題
ここでは僕の体験談を。
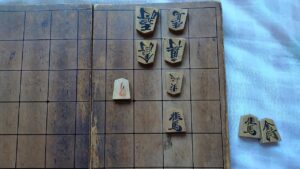
図は最近挑戦した問題で、3手必至をかけた局面です。
ただ恥ずかしい話ですが、僕はこの問題を解けませんでした。
▲2四桂までは見えましたが、ある応手への攻め方がわからなかったのです。
その応手とは…

△3七飛(粘られた図)でした。
正解を見ると以下
▲4一金 △同玉 ▲3二桂成 △同飛成
▲5三桂 △3一玉 ▲4一金 △同龍
▲同桂成 △同玉 ▲4二飛 △5一玉
▲5二と(正解図)

とのことでした。
僕は▲4一金~▲3二桂成の手順が見えず、完璧には読み切れませんでした。
この問題も△3七飛と粘ってから詰むまでは13手…
3手必至とはいえ、難問でした。
まとめ
今回のまとめは
・必至問題を解くのは初心者には難しい
・難しいのは詰ますまでに手数が長いこともあり、読み切るのが大変だから
・解説を読みながら盤に並べて、流れを味わうのがおすすめ
です。
必至問題は難しいので無理に解こうとはせず、解説を読みながら盤に並べるのがおすすめです。
難しいものを無理に解こうとすると、ストレスがたまります。
それでは将棋の楽しさを失ってしまうので、無理は避けましょう。
挑戦する気持ちになったら、そのときはぜひ挑んでみてください。
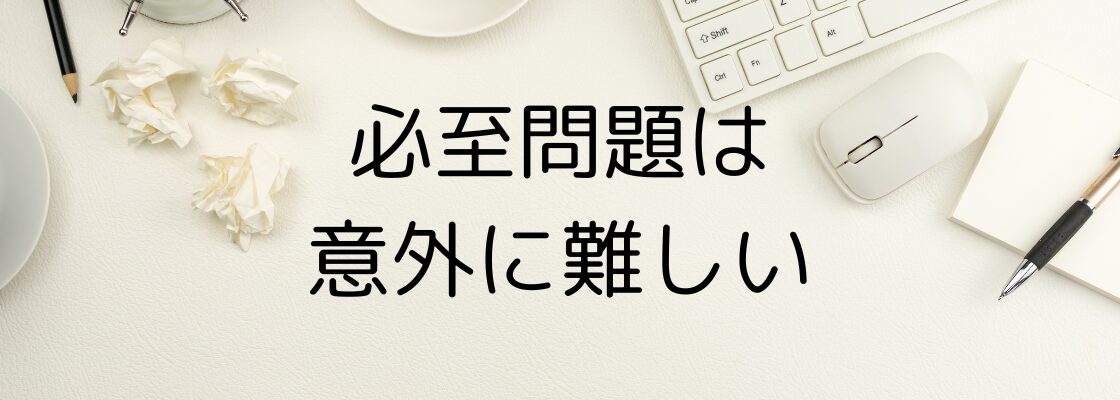
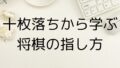
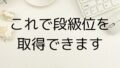
コメント